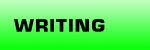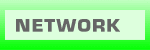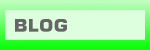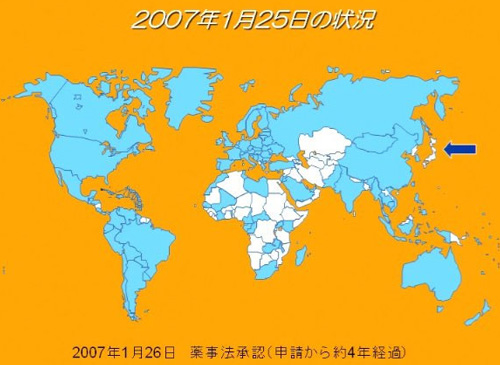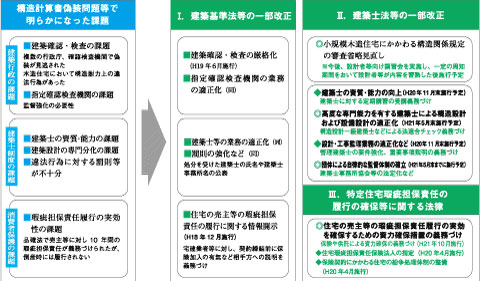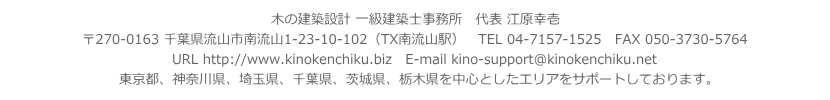�@�ŋ߁A���������ċz�nj�Q�iSAS�j���}�X�R�~�Ŏ��グ���邱�Ƃ������Ȃ����B�����P���Ԃ�����̖��ċz���ċz���P�O��ȏ�N����ꍇ�ɐ��������ċz�nj�Q�Ɛf�f�����B���������ċz�nj�Q�̍����ǂɂ͐S�؍[�ǁA���S�ǁA�]���Ǐ�Q�A�������A���A�a�Ȃǂ�����A���S���������Ȃ�̂Ő��������ċz�nj�Q�͊ʼn߂ł��Ȃ��a�C�ł���B
�@
�@����R���P�R���Ɍc��`�m��w�a�@�i�����s�V�h��j�ł`�o�g�iNPO�x�������nj�����j����Â���A�x�������ǂƐ��������ċz�nj�Q�ɂ��čl�������s��ꂽ�B�z����ȓc���Y���t��������Љ�Ȃ��畽�ՂȌ��t�ŕa�C�̐��������A���҂��[������܂Ŏ��^�������J��Ԃ��ꂽ�B

�c����t�ɔM�S�Ɏ��₷�銳�҂���B�B�e�E�]���K��
�@�x�������ǂ́A�S������x���t�𑗂�o�����ǂ������Ȃ��Ĕx�����̌����������Ȃ�a�C�ł���B�����Ǐ�́A�⓹��K�i��o��Ƃ��ɑ��ꂪ������A�ċz���ꂵ���Ȃ�����A��������݂����肷��B����ɐi�ނƐS�s�S���N�����A�����A���̂ނ��݂Ȃǂ��������B���_�A�P�A��ႂ��ł邱�Ƃ�����B�������s���̌������ƁA�P���a���V���S�����Ȃǂ������̓�������B���ẮA�x�������ǂ͔x�ڐA�ȊO�ɏ�������@���Ȃ��������S����������a�ł��������A���݂͎��ÖJ������A�������������Ȃ��Ă��Ă���B
�@
�@���������ċz�nj�Q�ɂ́A�얞�₠���̌`�������ŋC�����ǂ��ł��܂��ǐ����ċz�ƒ����_�o����ċz�̎i�߂������Ȃ����������ċz������B���Ö@�́A�ǐ����ċz�ɂ̓}�X�N��ʂ��ċC���Ɉ��͂�������b�o�`�o�Ö@�A���������ċz�ɂ͍ݑ�_�f�Ö@�iHOT�j�ƐS�s�S��p�̐l�H�ċz��iASV�j���g�����@������B
�@
�@���������ċz�nj�Q�Ɛf�f����Ď��ۂɂb�o�`�o�Ö@���{�������҂���́A�悭����Ĕ�ꂪ�Ƃ�A��ϊy�ɂȂ����Ƃ������z�������ꂽ�B
�@
�@�x�������ǂ̊��҂̒��ɂ͂悭����Ă��Ȃ��Ƃ������o�Ǐ��銳�҂��������A���ꂪ���������ċz�nj�Q�ł���Ǝ��o���Ă������҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B�c����t�͔x�������ǂ�S�s�S�̊��҂ɂ͒������̐��������ċz�nj�Q���������Ă��銳�҂��������ƂɌx����炵�A���̎��ÂɈӗ~�I�Ɏ��g��ł���B
�@
�@���������ċz�nj�Q�̎��Âɂ͕ی����K�p�����ꍇ������̂ŁA�^�킵���Ǝv����l�͐������f����Ƃ悢�B�c����t�́u���т������邳���v�u�����̖��C�������v�u�n�����������Ȃ��v�Ȃǂ̏Ǐ�����o����ꍇ�ɂ́A��x���������ċz�̗L�����m���߂錟�����s�����Ƃ����߂Ă���B
�@
�@�u���҂̎����v�𑣂��X�^�C���̈�Â��m�����Ă��Ȃ����{�ł́A�O�������ł͊��҂������̕a�C���Ƃ��Ƃ����A�S��[�����Ď��Â��邱�Ƃ͓���B���҂ƈ�t�̌𗬂̋��n���ɂȂ��Ă��銳�҉�̑��݈Ӌ`�͑傫���B
�@
�@
�����������ċz�nj�Q�i�c��`�m��w�a�@�j
�@http://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000265.html
�@
���x�������nj�����
�@http://www.aphj.org/
�@
�@����R���P�R���Ɍc��`�m��w�a�@�i�����s�V�h��j�ł`�o�g�iNPO�x�������nj�����j����Â���A�x�������ǂƐ��������ċz�nj�Q�ɂ��čl�������s��ꂽ�B�z����ȓc���Y���t��������Љ�Ȃ��畽�ՂȌ��t�ŕa�C�̐��������A���҂��[������܂Ŏ��^�������J��Ԃ��ꂽ�B

�c����t�ɔM�S�Ɏ��₷�銳�҂���B�B�e�E�]���K��
�@�x�������ǂ́A�S������x���t�𑗂�o�����ǂ������Ȃ��Ĕx�����̌����������Ȃ�a�C�ł���B�����Ǐ�́A�⓹��K�i��o��Ƃ��ɑ��ꂪ������A�ċz���ꂵ���Ȃ�����A��������݂����肷��B����ɐi�ނƐS�s�S���N�����A�����A���̂ނ��݂Ȃǂ��������B���_�A�P�A��ႂ��ł邱�Ƃ�����B�������s���̌������ƁA�P���a���V���S�����Ȃǂ������̓�������B���ẮA�x�������ǂ͔x�ڐA�ȊO�ɏ�������@���Ȃ��������S����������a�ł��������A���݂͎��ÖJ������A�������������Ȃ��Ă��Ă���B
�@
�@���������ċz�nj�Q�ɂ́A�얞�₠���̌`�������ŋC�����ǂ��ł��܂��ǐ����ċz�ƒ����_�o����ċz�̎i�߂������Ȃ����������ċz������B���Ö@�́A�ǐ����ċz�ɂ̓}�X�N��ʂ��ċC���Ɉ��͂�������b�o�`�o�Ö@�A���������ċz�ɂ͍ݑ�_�f�Ö@�iHOT�j�ƐS�s�S��p�̐l�H�ċz��iASV�j���g�����@������B
�@
�@���������ċz�nj�Q�Ɛf�f����Ď��ۂɂb�o�`�o�Ö@���{�������҂���́A�悭����Ĕ�ꂪ�Ƃ�A��ϊy�ɂȂ����Ƃ������z�������ꂽ�B
�@
�@�x�������ǂ̊��҂̒��ɂ͂悭����Ă��Ȃ��Ƃ������o�Ǐ��銳�҂��������A���ꂪ���������ċz�nj�Q�ł���Ǝ��o���Ă������҂͂قƂ�ǂ��Ȃ������B�c����t�͔x�������ǂ�S�s�S�̊��҂ɂ͒������̐��������ċz�nj�Q���������Ă��銳�҂��������ƂɌx����炵�A���̎��ÂɈӗ~�I�Ɏ��g��ł���B
�@
�@���������ċz�nj�Q�̎��Âɂ͕ی����K�p�����ꍇ������̂ŁA�^�킵���Ǝv����l�͐������f����Ƃ悢�B�c����t�́u���т������邳���v�u�����̖��C�������v�u�n�����������Ȃ��v�Ȃǂ̏Ǐ�����o����ꍇ�ɂ́A��x���������ċz�̗L�����m���߂錟�����s�����Ƃ����߂Ă���B
�@
�@�u���҂̎����v�𑣂��X�^�C���̈�Â��m�����Ă��Ȃ����{�ł́A�O�������ł͊��҂������̕a�C���Ƃ��Ƃ����A�S��[�����Ď��Â��邱�Ƃ͓���B���҂ƈ�t�̌𗬂̋��n���ɂȂ��Ă��銳�҉�̑��݈Ӌ`�͑傫���B
�@
�@
�����������ċz�nj�Q�i�c��`�m��w�a�@�j
�@http://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000265.html
�@
���x�������nj�����
�@http://www.aphj.org/